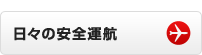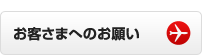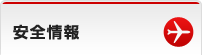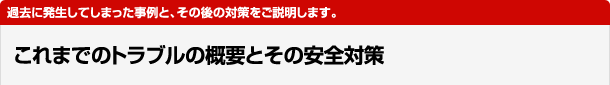| 636便飛行中の揺れによるお客さまの負傷 | |
| 3228便の機体損傷 | |
| 2576便の着陸復行 | |
| 日本エアコミューター2345便の着陸時の滑走路逸脱 | |
| 502便の管制指示違反 | |
| 958便離着陸時に化粧室内にカートを収納した事例 | |
| 1280便の滑走路進入について |
航空機の運航によって発生した人の死傷(重傷以上)、航空機の墜落、衝突または火災などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
| 636便飛行中の揺れによるお客さまの負傷 | |
|---|---|
| 概要 | 2007年10月27日、日本航空636便(中国・杭州空港発/成田空港行き)は、成田国際空港への降下中、タービュランス(乱気流による揺れ)に遭遇し、その際、お客さま1名が負傷されました。着陸後、お客さまからのお申し出があり、空港の診療所や近くの病院で診察を受けられましたが異常は見つからず、2日後に再度別の病院で診察を受けられた結果、胸椎(きょうつい)の骨折であることが判明しました。これを受けて、10月30日、本件は国土交通省により「航空事故」と認定されました。 |
| 原因究明など | 国土交通省運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2008年12月19日付けで公表されました。報告書によると同機が降下中に、シートベルト・サインがオンの状態で、台風の北側に発生した前線帯を通過したことによって、激しい気流の擾乱に遭遇した際に、機体が大きく動揺し、お客さまが膝の上に抱えていた手荷物が、シートベルトの留め金具に接触してシートベルトが外れ、座席から体が飛び出して前席の背もたれに腰を強打し負傷されたものと推定されています。 |
| 対策 | タービュランスによる負傷防止については、主に以下の項目に取り組んでいます。
|
| 3228便の機体損傷 | |
|---|---|
| 概要 | 2008年3月11日、日本航空3228便(福岡空港発/中部国際空港行き)は、福岡空港離陸上昇中に操縦室前方下部より異音と振動が発生しました。運航乗務員は手順に従いエンジン計器指示、客室内与圧値などが正常であることを確認のうえ飛行を継続し、中部国際空港に着陸しました。到着後の点検で、前方右側胴体に鳥衝突とみられる損傷(へこみ)と前脚格納室内部構造の一部に変形とひびが発見されました。この損傷は航空法に定める大修理に相当するため、3月13日、本件は国土交通省により「航空事故」と認定されました。 |
| 原因究明など | 国土交通省運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2008年9月19日付けで公表されました。報告書によると、同機は離陸上昇中に渡り鳥と衝突したため、機体を損傷したものと推定されています。 |
航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
| 2576便の着陸復行 | |
|---|---|
| 概要 | 2007年10月20日、日本航空2576便(那覇沖縄空港発/関西空港行き)は、管制の着陸許可を得て関西国際空港のA滑走路に進入中、同滑走路からの出発を予定していたエアカナダ036便が管制からの滑走路手前での待機指示に反して同滑走路に入ったため、管制の指示により着陸復行しました。なお、お客さまおよび乗員に怪我はございませんでした。本件は国土交通省より「重大インシデント」に認定されましたが、これは関連機としての扱いであり、事態発生原因への関与はありません。 |
| 原因究明など | 国土交通省運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2009年2月27日付けで公表されました。報告書によると、滑走路手前で待機するよう指示されたエアカナダ機の運航乗務員がその指示を間違えて滑走路に進入する旨の復唱を行ない、管制官もその復唱内容を誤認して確認しなかったことから、エアカナダ機がそのまま滑走路に進入したため、既に管制官から着陸許可を受けていた日本航空機が着陸復行をする事態になったと推定されています。 |
| 日本エアコミューター2345便の着陸時の滑走路逸脱 | |
|---|---|
| 概要 | 2007年12月18日、日本エアコミューター2345便(伊丹空港発/出雲空港行き)は、出雲空港着陸後、機体が右側に偏向しはじめ、滑走路中央付近から芝生エリアおよび誘導路を横切り、駐機場に入ったところで停止しました。停止後に確認したところ、前輪左側のタイヤがパンクし、右側のタイヤが外れていたことが判明しました。なお、お客さまおよび乗員に怪我はございませんでした。本件は国土交通省より「重大インシデント」に認定されました。 |
| 原因究明など | 国土交通省運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2009年8月28日付けで公表されました。報告書によると、接地とほぼ同時に左プロペラがコースン・ピッチとなり、走行中に右方向に機首が偏向していった際に、偏向を止め、さらには修正するために必要な操縦操作が行われなかったため、滑走路から逸脱し、前脚が破損して、自ら地上走行できなくなったものと推定されています。左プロペラがコースン・ピッチになったことについては、接地前に行われたパワーレバー操作によりオートコースンシステム(*1)が作動したことによるものと推定されています。 *1. オートコースン・システム 離陸時や着陸復行時に片側のエンジンが不調になった場合に、パイロットの操作を軽減するために、その不調となった側のプロペラをフェザー(プロペラの角度を進行方向と平行にして抵抗を減らす)状態にする機能です。 |
| 対策 | 日本エアコミューターおよび同型機を運航する北海道エアシステムにおいては、運航乗務員に対し、オートコースン・システムに関する留意事項を含め、当該システムの特性について関連規程類による再確認を行うことを指示するとともに、教育を実施しました。 |
| 502便の管制指示違反 | |
|---|---|
| 概要 | 2008年2月16日、日本航空502便(新千歳空港発/羽田空港行き)は、管制より「直ちに離陸をしなくてはならないことを予期すること。」との指示に対して適切な復唱を行わず離陸許可が出されたものと認識して離陸滑走を開始しました。その直後、管制より離陸中止を指示され、離陸を中止しました。スポットに引き返した後、当該便は離陸許可を受けずに離陸滑走を開始したこと、およびその時点ではまだ着陸機が滑走路上にいたことを知らされました。なお、お客さまおよび乗員に怪我はございませんでした。本件は国土交通省により「重大インシデント」に認定されました。 |
| 原因究明など | 国土交通省運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2009年1月23日付けで公表されました。報告書によると、当該機が離陸許可を受けないまま離陸滑走を開始したことについては、通常は使用しない「IMMEDIATE TAKE-OFF」を含む管制情報を管制官が通報し、当該機の機長が「迅速な離陸の指示」を受けたものと錯誤し、さらに他の運航乗務員からの助言もなかったことによるものと推定されています。 また、報告書には、国土交通大臣に対して、以下の「意見」(*2)が付されました。 *2. 意見 運輸安全委員会が、必要があると認めたときに、国土交通大臣または関係行政機関の長に対して被害の軽減のために講じる施策について述べる。 意見:当委員会は、本重大インシデント調査の結果に鑑み、航空交通の安全を確保するため、国土交通大臣に対して、運輸安全委員会設置法に基づき、以下のとおり意見を述べる。
|
| 対策 | 本件につきましては、発生直後から以下の対策を実施しました。
|
2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。
| 安全上のトラブルの分類と具体例 |
|---|
| 被雷や鳥の衝突などによる航空機の損傷 / システムの不具合 (例) エンジントラブル、通信・電気系統のトラブル |
| 非常時に作動する機器などの不具合 (例) 火災・煙の検知器の故障 |
| 規定値を超えた運航 (例) 決められた限界速度を超過 |
| 機器からの指示による急な操作など (例) TCAS(衝突防止警報装置)などの指示に基づく操作 |
以下2件の事例につきましては、航空事故、重大インシデント、安全上のトラブルのいずれにも該当しません。
| 958便離着陸時に化粧室内にカートを収納した事例 | |
|---|---|
| 概要 | 2008年2月6日、日本航空958便(プサン空港発/成田空港行き)において、機内食カート1台が所定の場所に収納できず、化粧室に入れた状態で離着陸しました。 |
| 対策 | 本件の再発防止については、以下の項目に取り組みました。
|
| 1280便の滑走路進入について | |
|---|---|
| 概要 | 2008年3月4日、日本航空1280便(小松空港発羽田空港行き)は、管制より滑走路手前で停止する指示を受けこれを復唱しましたが、誘導路近くは夜間で暗く遠方から停止位置標識を確認しにくい状況の中、これを越えて滑走路に進入しました。当該便は直ちに管制に状況を報告するとともに、進入機のライトを視認していたので、管制に進入機の着陸復行を依頼。進入機の着陸復行後、当該便は、管制の指示に従って離陸しました。 | 原因究明など | 誘導路付近は夜間で暗く遠方から停止位置標識を確認しにくい状況の中、訓練中の副操縦士とその教官役の機長との間で相互の役割分担が曖昧となり、両者の前方への注意が疎かになったことで、停止位置標識を見つけることが出来ずこれを越え使用滑走路に進入したと推定しました。 |
| 対策など | 本件発生後、直ちに全運航乗務員への事例周知と注意喚起を行いました。 本件と先の日本航空502便事例がともに訓練中に発生していることに鑑み、2008年3月6日より路線運航におけるすべての訓練や教育を中止したうえで、多数の運航乗務員からヒアリングなどを通じて現状の問題点などを調査した結果、いずれも訓練や教育を実施している最中に発生したヒューマンエラーを適切にマネジメントできなかったことが把握できました。主に以下の改善措置を講じることにより、訓練および教育を実施する場合の安全性は十分に確保することができると判断したため、これらを直ちに実行に移したうえで、路線訓練を2008年4月5日より順次再開しました。 (主な改善措置) 路線運航にあっては、たとえ訓練を行う場合であっても、必要な安全上の指摘や助言をして、チームとしてのパフォーマンスを高めることが大前提であることを、教官および訓練生双方に対し、あらためて周知徹底しました。 空港施設などにかかわるスレット(エラーを誘発する要因)となる情報を収集し、それらを周知します。また、関係機関との調整により、スレットの軽減を図る体制を再構築するといった改善措置も検討します。 副操縦士路線訓練において、副操縦士候補者が操縦席に着席し、訓練にあたるための条件の制限、および同乗する副操縦士資格者の要件の見直しをします(環境上の制限、経験上の制限)。 |