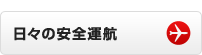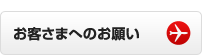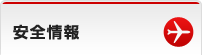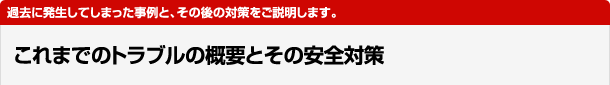| 2375便飛行中の揺れによる客室乗務員の負傷 | |
| 950便飛行中のサービスカート上のお茶によるお客さまの火傷 | |
| 日本エアコミューター2409便のエンジン不具合 | |
| 日本エアコミューター3760便のエンジン不具合 |
航空機の運航によって発生した人の死傷(重傷以上)、航空機の墜落、衝突または火災などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
| 2375便飛行中の揺れによる客室乗務員の負傷 | |
|---|---|
| 概要 | 2008年12月9日、日本航空2375便(大阪国際空港発/長崎空港行き)は、上昇中高度約25,000フィートで突然の揺れに遭遇し、後方ギャレーでサービスの準備中であった客室乗務員2名が負傷しました。長崎空港到着後、病院にて1名は右足関節内果、後果骨折と右足関節外側靱帯損傷、もう1名は第1腰椎骨折と頚部捻挫と診断されました。これを受けて同日、本件は国土交通省により航空事故と認定されました。 |
| 原因究明など | 国土交通省運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2010年2月26日付けで公表されました。報告書によると、同機が大阪国際空港を離陸し上昇中、シートベルト着用サインを消灯した状態で、上空のジェット気流下面に発達した前線帯を通過したため、強い風の変化による気流の乱れにより同機が大きく揺れ、客室後方調理室で作業中の二人の客室乗務員が重傷を負ったものと推定されています。 |
| 対策 | タービュランスによる負傷防止のため、以下の項目を実施しました。 運航乗務員が出発前に確認する気象情報を時系列で掲示し、タービュランス情報の状況変化を把握しやすくしました。 タービュランス情報を通報する航空機の範囲を広げ、発生する位置や強度の予測が難しいタービュランスへの警戒を高めるようにしました。 また、引き続き、運航乗務員、運航管理者に対する気象にかかわる教育の充実を図っていきます。 |
| 950便飛行中のサービスカート上のお茶によるお客さまの火傷 | |
|---|---|
| 概要 | 2009年1月27日、日本航空950便(ソウル(仁川)空港発/成田国際空港行き)は、高度7,000フィートでの水平飛行中、サービスカートによる食事・飲み物サービスを開始しましたが、その後の上昇中にサービスカートが移動し、座席に当たって傾いて停止しました。その衝撃でカート上の日本茶のポットが倒れ、お客さま1名の右上腕部にかかり、火傷されました。本件は1月30日韓国当局より「航空事故」と認定されました。 |
| 原因究明など | 本件は、韓国当局より委任された国土交通省運輸安全委員会に原因究明などの調査が委ねられています。当社は同委員会の調査に全面的に協力するとともに、必要な対策を行っていきます。 |
航空事故には至らないものの、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
| 日本エアコミューター2409便のエンジン不具合 | |
|---|---|
| 概要 | 2008年8月12日、日本エアコミューター2409便(伊丹空港発/鹿児島空港行き)は、 伊丹空港を離陸滑走中、左側エンジンが異音とともに出力が落ちたため、離陸を中止しました。機体停止後、両エンジンの計器指示値は正常でしたが、左側エンジンの出力を絞り、駐機場へ引き返しました。なお、お客さまおよび乗員に怪我はございませんでした。 点検の結果、機体の損傷はありませんでしたが、エンジン内部のタービンブレード (翼)の一部に破損が認められました。この破損は、航空法施行規則に定める「発動機の破損(エンジンの内部において大規模な破損が生じた場合)」に相当するため、8月13日、本件は国土交通省により重大インシデントと認定されました。 |
| 原因究明など | 国土交通省運輸安全委員会により調査が行なわれ、その結果が2010年2月26日付けで公表されました。報告書によると、エンジンの高圧タービン外周部分が熱で劣化し、溶解した物質が後段の低圧タービンに付着。タービンの冷却が損なわれて損傷、脱落、後段の高速回転部分に入り、内部の大規模な損傷を誘発した結果、エンンジンの急激な出力低下に至ったものと推定されています。 |
| 対策 | 再発防止のため、以下の対策を実施しました。 エンジン製造会社に対して、整備処置要領の明確化を要求し、エンジン製造会社はその改訂を行いました。 エンジンの不具合を事前に予知するための監視システムの整備を行いました。 今後も機材品質向上のための取り組みを強化していきます。 |
| 日本エアコミューター3760便のエンジン不具合 | |
|---|---|
| 概要 | 2009年3月25日、日本エアコミューター3760便(種子島空港発/鹿児島空港行き)は、種子島空港を離陸上昇中、左側エンジンの滑油圧力の低下を示す計器表示があったため当該エンジンを停止し、航空交通管制上の優先権を要請のうえ、鹿児島空港に着陸しました。 到着後の点検の結果、第1エンジンのギアボックス接続部およびタービンブレード等に損傷が認められました。この破損は、航空法施行規則に定める「発動機の破損(エンジンの内部において大規模な破損が生じた場合)」に相当するため、本件は同日、国土交通省により重大インシデントと認定されました。なお、お客さまおよび乗員に怪我はございませんでした。 |
| 原因究明など | 本件は国土交通省運輸安全委員会による調査が行なわれ、その結果が2010年8月27日付けで公表されました。報告書によると、エンジン内部の部品が破損したことが原因であると推定されています。具体的には、当該機の離陸上昇中に左側エンジンの回転軸が折れ、その影響でその周辺部品が破損しました。この破損した部品の破片が飛散し、エンジンのタービンブレード等に損傷を与えたためにエンジントラブルに至ったものです。 また、回転軸が折れた原因は、回転軸の製造段階で不純物が混入したことで、本来の耐久性が損なわれたためと推定されています。 |
| 対策 | 回転軸が折れたことに対する暫定的な対策として、エンジンの製造会社から航空会社に対し、回転軸の特別点検を直ちに実施するよう指示が出されました。これを受けて日本エアコミューターにおいても点検を実施し、その他の機体の回転軸に異常のないことを確認致しました。 また、恒久的な対策として、エンジンの製造会社より不純物混入の可能性のある回転軸について、新品に交換するよう指示が出され、日本エアコミューターではこれに従い、対象となる回転軸をすべて交換致しました。 さらに、運輸安全委員会は、航空機とエンジンの設計・製造国であるカナダの航空局に対して、エンジンの製造会社における回転軸の製造品質管理を改善するために必要な処置を講じるよう安全勧告を行いました。 |
2006年10月1日付施行の法令(航空法第111条の4および航空法施行規則第221条の2第3号・第4号)に基づき、新たに国土交通省に報告することが義務付けられたもので、以下の事態が該当します。
このようなトラブルは、トラブルの要因が積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものですが、直ちに航空事故の発生につながるものではありません。
| 安全上のトラブルの分類と具体例 |
|---|
| 被雷や鳥の衝突などによる航空機の損傷 / システムの不具合 (例) エンジントラブル、通信・電気系統のトラブル |
| 非常時に作動する機器などの不具合 (例) 火災・煙の検知器の故障 |
| 規定値を超えた運航 (例) 決められた限界速度を超過 |
| 機器からの指示による急な操作など (例) TCAS(衝突防止警報装置)などの指示に基づく操作 |