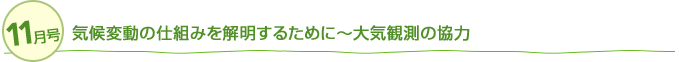今月末より、南アフリカ・ダーバンで、「国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP17)」が開かれます。地球温暖化対策の次期枠組み(ポスト京都議定書)の合意を目指した議論が行われ、有効な枠組みの成立が期待されています。
この条約には、COPの他にも分野別の専門的な常設会議があり、昨年行われた会議では、「研究と組織的観測」について議論が行われ、日本政府からこの分野への日本の貢献として、「温室効果ガス観測技術衛星いぶき(GOSAT)による宇宙からの二酸化炭素やメタンの濃度分布観測」と「民間航空機による大気観測」が紹介されました。
JALは、この両プロジェクトに協力しています。「大気観測」は、気象研究所などとともに、大気の変動メカニズムを地球規模で解明するために、1993年から開始。現在は、国立環境研究所、気象研究所らと共同の「CONTRAILプロジェクト」に発展し、定期便にて大気の自動採取、機上でのCO2 濃度測定を行っています。長期間にわたり蓄積された膨大なデータは、世界中の研究者から「JALデータ」と呼ばれ、さまざまな研究に役立てられています。そしてこの「JALデータ」は、「いぶき」の観測精度向上にも役立てられているのです。
かつてボーイング747-400型機に搭載されていた大気の自動採取装置は、航空機の退役に伴い、この春777型機に載せ替えられました。
「大気中に含まれる極微量の成分を正確に測定するためには、機内を循環する空気と混ざらないことが条件となります。このため、観測装置を搭載するほかにも、新鮮な空気だけを取り込めるように特別な配管を施した独自の改修を、航空機部品製造メーカーのジャムコ社と協力して実施しています。小型化された航空機に対して、より限られた狭いスペースの中、何度も検証して搭載場所を探すのに大変苦労しました」(技術部の宗さん)
航空機を改修し、新しい機器を搭載するには、日米当局が定めた基準と非常に厳しい検査をクリアする必要があり、高度な技術力が求められます。
「JALグループの高い技術力は、航空機の安全はもちろんのこと、地球環境を守るためにも役立っています」(同)
JALはこれからも、航空会社ならではの方法で、気候変動緩和に向けた取り組みに協力していきます。
JALグループでは、さまざまな環境活動に取り組んでいます。航空会社ならではの取り組みを、現場の声を交えて、これからもお伝えしていきます。また、ホームページでも多彩な活動をご紹介しています。
![]()
 6月号 空の旅の新しい選択〜JALカーボンオフセット
6月号 空の旅の新しい選択〜JALカーボンオフセット 7月号 窓の日よけを下ろして、お客様とともにエコ活動を
7月号 窓の日よけを下ろして、お客様とともにエコ活動を 8月号 空から見守る地球環境〜森林火災の発見通報
8月号 空から見守る地球環境〜森林火災の発見通報 9月号 先進的な運航方式で、エコに飛んでいます!
9月号 先進的な運航方式で、エコに飛んでいます! 10月号 航空機で大気観測〜「JALデータ」で温暖化メカニズム解明に協力
10月号 航空機で大気観測〜「JALデータ」で温暖化メカニズム解明に協力 11月号 パイロットが取り組むエコ・フライト活動
11月号 パイロットが取り組むエコ・フライト活動 12月号 鳥のように軽やかに〜機体軽量化への取り組み
12月号 鳥のように軽やかに〜機体軽量化への取り組み 1月号 美しく豊かな地球を次世代へつなぐために
1月号 美しく豊かな地球を次世代へつなぐために 2月号 エンジンもシャワーですっきり!〜定期洗浄で燃費向上
2月号 エンジンもシャワーですっきり!〜定期洗浄で燃費向上 3月号 ボーイング787〜環境に、人に優しい新型航空機
3月号 ボーイング787〜環境に、人に優しい新型航空機 8月号 シェードを下ろして、電力と石油資源の節約を
8月号 シェードを下ろして、電力と石油資源の節約を 9月号 コックピットから見た地球の変化を伝える
9月号 コックピットから見た地球の変化を伝える 10月号 森林火災の情報提供により、世界の森を守る
10月号 森林火災の情報提供により、世界の森を守る 11月号 気候変動の仕組みを解明するために
11月号 気候変動の仕組みを解明するために 12月号 Time is eco 〜定時運航で時間と環境を大切に〜
12月号 Time is eco 〜定時運航で時間と環境を大切に〜 1月号 地球や自然との調和を築く〜JALエコジェット・ネイチャー
1月号 地球や自然との調和を築く〜JALエコジェット・ネイチャー 2月号 空育〜子どもたちと一緒に地球の「いま」を考える
2月号 空育〜子どもたちと一緒に地球の「いま」を考える 最新号
最新号
![]()