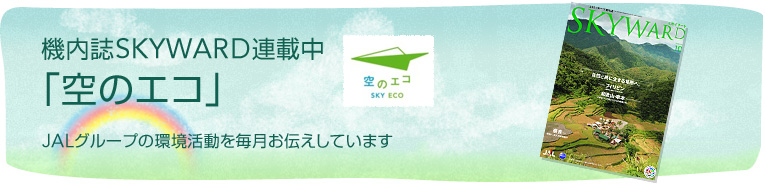1992年、ブラジル・リオデジャネイロで地球サミットが開かれ、各国が協力して地球温暖化問題に取り組むことに初めて合意し、「気候変動枠組条約(UNFCCC)」が締結されました。当時は、地球温暖化についての認識は一般的に低く、科学的にも解明されていないことがたくさんありました。
地球温暖化に有効な対策を取るためには、将来の気候変動を正確に予測することが必要です。特に、温室効果ガスのうち量的にもっとも影響が大きいとされているCO2が、地球規模でどのように循環し、海洋や陸域でどのように放出・吸収されているのかを正確に把握するための観測が重要といわれています。CO2 観測のほとんどは、地上の定点で行われていますが、三次元的な分布を補うために、船舶やチャーター航空機などが用いられます。しかし、観測が行われていない地域がいまだ多数あり、上空のデータは極めて限られているのが現状です。
UNFCCC締結の翌年、JALは日航財団、気象庁気象研究所と共同で、「温室効果ガスを含む大気成分の地球規模での変動メカニズムの解明」に協力するため、民間航空会社としては世界で初めて定期便での大気観測を開始しました。以来2005年までの間、オーストラリア─日本間の定期便ルート上で、月に2回大気を自動採取した結果、南北半球にまたがる上層大気の温室効果ガス濃度の長期変動などの解明につながりました。
2005年11月からは、大気の自動採取に加え、機上でCO2濃度を測定できる装置を開発し、国立環境研究所や気象研究所等と新たに「CONTRAILプロジェクト」として活動。新装置の搭載により、アフリカと南米を除く世界各地と日本間で膨大なデータが得られています。
これまでの観測で得られたデータは「JALデータ」と呼ばれ、世界に例のない貴重なデータとして、各国研究者から注目を集めています。これらを分析した結果、季節、高度、地域によるCO2濃度の変動など、CO2の循環メカニズムが明らかになったばかりでなく、地球上の大気の動きについても、新しい発見へとつながっています。また最近では、温室効果ガス観測衛星「いぶき」の観測精度向上にも役立てられています。
*最新号は機内でお楽しみいただけます。
JALではさまざまな環境への取り組みを行っています。その一環として、生物多様性の取り組みに協力。今月開催の「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」のロゴを機体に描いた「COP10エコジェット」も就航しています。また、「JAL Happy Eco Project」のホームページでは、COP10名誉大使を務める、アーティストMISIAさんのスペシャルインタビューも公開中!ぜひご覧ください。
![]()
 6月号 空の旅の新しい選択〜JALカーボンオフセット
6月号 空の旅の新しい選択〜JALカーボンオフセット 7月号 窓の日よけを下ろして、お客様とともにエコ活動を
7月号 窓の日よけを下ろして、お客様とともにエコ活動を 8月号 空から見守る地球環境〜森林火災の発見通報
8月号 空から見守る地球環境〜森林火災の発見通報 9月号 先進的な運航方式で、エコに飛んでいます!
9月号 先進的な運航方式で、エコに飛んでいます! 10月号 航空機で大気観測〜「JALデータ」で温暖化メカニズム解明に協力
10月号 航空機で大気観測〜「JALデータ」で温暖化メカニズム解明に協力 11月号 パイロットが取り組むエコ・フライト活動
11月号 パイロットが取り組むエコ・フライト活動 12月号 鳥のように軽やかに〜機体軽量化への取り組み
12月号 鳥のように軽やかに〜機体軽量化への取り組み 1月号 美しく豊かな地球を次世代へつなぐために
1月号 美しく豊かな地球を次世代へつなぐために 2月号 エンジンもシャワーですっきり!〜定期洗浄で燃費向上
2月号 エンジンもシャワーですっきり!〜定期洗浄で燃費向上 3月号 ボーイング787〜環境に、人に優しい新型航空機
3月号 ボーイング787〜環境に、人に優しい新型航空機 8月号 シェードを下ろして、電力と石油資源の節約を
8月号 シェードを下ろして、電力と石油資源の節約を 9月号 コックピットから見た地球の変化を伝える
9月号 コックピットから見た地球の変化を伝える 10月号 森林火災の情報提供により、世界の森を守る
10月号 森林火災の情報提供により、世界の森を守る 11月号 気候変動の仕組みを解明するために
11月号 気候変動の仕組みを解明するために 12月号 Time is eco 〜定時運航で時間と環境を大切に〜
12月号 Time is eco 〜定時運航で時間と環境を大切に〜 1月号 地球や自然との調和を築く〜JALエコジェット・ネイチャー
1月号 地球や自然との調和を築く〜JALエコジェット・ネイチャー 2月号 空育〜子どもたちと一緒に地球の「いま」を考える
2月号 空育〜子どもたちと一緒に地球の「いま」を考える 最新号
最新号
![]()