外部イニシアティブへの参画
こちらの表は横スクロールできます
| イニシアティブ・団体名 | ロゴ | 概要 |
|---|---|---|
| 国連グローバル・コンパクト(UNGC) |  |
1999年1月のコフィー・アナン国連事務総長による提唱のもと、翌2000年7月正式に発足し、 世界各国の参加企業に対して人権・労働・環境・腐敗防止の10原則を実践することを求めている団体です。 JALグループは、2004年12月よりグローバル・コンパクトに参加し、 お客さま、文化、そしてこころを結ぶ企業活動を通じて、グローバル・コンパクトの10原則を確実に実践し、 日本と世界の平和と繁栄に貢献しています。 |
| グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ) | - | グローバル・コンパクトの日本におけるローカル・ネットワークとして、 会員の協力と貢献のもとにグローバル・コンパクト10原則の実践を積極的に推進するとともに、広く海外に情報発信し、 21世紀の望ましいグローバル社会の形成に寄与することをその目的とする団体です。 |
| 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD) |  |
TCFDは、G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により、気候関連の情報開示および金融機関の対応をどのように行うかを検討するため、2015年に設立されました。JALは2021年2月にTCFDの提言に賛同し、2021年8月にTCFDに沿った情報開示を行いました。また、2021年9月からは「TCFDコンソーシアム」にも参加しています。 今後も定期的にTCFDおよびその後継となるISSB基準に則った情報開示を実施していきます。 |
| GXリーグ別ウィンドウで開く |  |
GXリーグとは、2050年カーボンニュートラル実現と社会変革を見据えて、GXヘの挑戦を行い、現在および未来社会における持続的な成長実現を目指す企業が同様の取り組みを行う企業群を官・学と共に協働する場です。 JALグループは2024年度より参画し、他業界や企業との連携により日本国内における中長期的なCO2削減を推進していきます。 |
| 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)別ウィンドウで開く |  |
脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち積極的な行動を開始すべきであるという認識のもと、2009年に発足した企業団体です。幅広い業界から日本を代表する企業が加盟しており、脱炭素社会実現への転換期において、社会から求められる企業となることを目指しています。 2017年より The Climate Group の公式地域パートナーとして、日本における RE100、EV100、EP100 イニシアチブの窓口・運用を担っています。自治体との連携協定や日本独自の新たな枠組み再エネ100宣言 RE Action を共同主催するなど、さまざまな連携も進めています。 JALは2018年から賛助会員として参加しています。 |
| エコ・ファースト推進協議会別ウィンドウで開く |  |
企業が環境分野において「先進的、独自的でかつ業界をリードする事業活動」を 行っているとして環境省から認定されている「エコ・ファースト企業」が、 連携して環境保全活動を推進していくことを目的に設立された協議会です。 JALグループは2010年に「エコ・ファースト企業」として認定されたのち、 2016年度より本協議会に加盟しています。 |
| 経団連「チャレンジ・ゼロ」(チャレンジ ネット・ゼロカーボン イノベーション) |  |
経団連が日本政府と連携し、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」が長期的なゴールと位置づける「脱炭素社会」の実現に向け、企業・団体がチャレンジするイノベーションのアクションを、国内外に力強く発信し、後押ししていくイニシアティブです。 2020年の発足以来、JALグループは当イニシアティブに参画し、取り組みを公表しています。 |
| 東京湾岸ゼロエミッションイノベーション協議会 (ゼロエミベイ)別ウィンドウで開く | 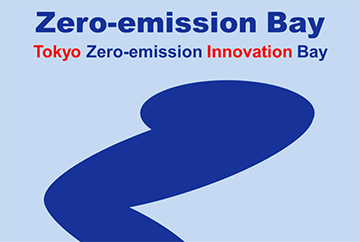 |
「革新的環境イノベーション戦略」(令和2年1月21日内閣府の統合イノベーション戦略推進会議にて決定)に基づき、東京湾岸周辺エリアに存在する企業、大学、研究機関、行政機関等の研究開発・実証、ビジネスなどでの連携を促進することにより、東京湾岸周辺エリアを世界に先駆けてゼロエミッション技術に係るイノベーションエリアとすることを目的として設立された団体です。 2020年の発足以来、JALグループは当協議会に参画し、情報収集や意見交換を実施しています。 |
| 気候変動イニシアティブ(JCI)別ウィンドウで開く |  |
JCIは気候変動対策に積極的に取り組む企業や自治体、NGOなどの情報発信や意見交換を強化するため設立されたネットワークです。 JALグループは2021年より参画し、参加メンバーとともにネット・ゼロエミッションの実現に向けて取り組んでいます |
| 世界経済フォーラム(WEF) Clean Skies for Tomorrow |
 |
グローバルかつ地域的な経済問題に取り組むために、政治、経済、学術などの各分野における 指導者層の交流促進を目的とした独立・非営利団体です。 本団体が中心となり、航空業界の2050年CO2排出量実質ゼロに向けて2030年に 使用燃料の10%をSAFにするというMission Possible StatementにJALグループも賛同しています。 |
| ACT FOR SKY別ウィンドウで開く |  |
国産SAF(持続可能な航空燃料)の商用化および普及・拡大に取り組む有志団体で2022年3月2日に日揮ホールディングス、レボインターナショナル、全日本空輸およびJALが幹事会社となり設立、14社のメンバーでスタートしました。「ACT=行動を起こす」意志を持つ企業が協調・連携し、SAFやカーボンニュートラル、資源循環の重要性を訴えながら市民・企業の意識変革を通じて、行動変容につなげていくことを目指します。2024年9月末時点で加盟企業・団体は45社まで増えており、定期的な会合でさまざまな情報交換や勉強会を開催するとともに、2024年12月には初めてとなるACT FOR SKYシンポジウムの開催を予定しています。 |
| FRY to FLY Project別ウィンドウで開く |  |
設立主旨に賛同する29の参加企業・自治体・団体(2023年4月17日時点)が相互に連携しつつ、家庭や飲食店などから排出される廃食用油が資源として回収されるための環境づくりを促進するとともに、日本国内において脱炭素化に向けた資源循環の促進に積極的に参加できる機会の創出を目指すものです。現在100を超えるメンバー数となっておりますが、JALグループは開始当初から参加し、この取り組みを通じて「すてる油で空を飛ぼう」という家庭から排出される廃食油を回収する仕組みの構築を進めています。 |
| 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン) |  別ウィンドウで開く 別ウィンドウで開く |
WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年に設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止などの活動を行なっています。 WWFジャパンは1971年に正式に発足し、JALは2020年よりWWFジャパンの会員として当団体の活動に賛同しています。また、WWFジャパンが呼びかける「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」に参画し、プラスチック問題の解決に取り組んでいます。 |
| プラスチックスマート別ウィンドウで開く |  |
環境省では、世界的な海洋プラスチック問題の解決に向けて、個人・自治体・NGO・企業・研究機関など幅広い主体が連携協働して取り組みを進めることを後押しするため、「プラスチック・スマート -for Sustainable Ocean-」と銘打ったキャンペーンを2018年10月に立ち上げています。 JALはこのキャンペーンに参加し、海洋プラスチック問題の解決に向けた取り組みを行っています。 |
| 健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ別ウィンドウで開く | - | 人々がより健康的な食生活を送れるよう、人々の食品(食材、料理、食事)へのアクセスと情報へのアクセスの両方を、相互に関連させて整備していく「食環境づくり」を厚生労働省主体に、産学官等が連携して進める取り組みです。 JALは2022年から参画し、食品による健康への負の影響や、より良い栄養へのアクセスを考慮しながら、JALの取り組みに生かしています。 |
| あふの環プロジェクト (あふの環2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~)別ウィンドウで開く |
 |
農林省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ地球環境対策室が主催する「持続的な生産消費」に向けた取り組みを進める企業や団体の合同プロジェクトです。 「スペンドシフト~サステナブルを日常に、エシカルを当たり前に!~」を合言葉に,生産から消費までのステークホルダーの連携を促進し、食料や農林水産業に関わる持続的な生産消費を達成することを目指しています。 JALはこのプロジェクトに参画し、持続的な食材を使用した機内・ラウンジ食の実現に向けた取り組みを行っています。 |
| GAP パートナー別ウィンドウで開く | - | 農林省農産局農業環境対策課が運営する、消費者にも環境にもGOODなGAPの価値を共有し、GAP認証農産物を取り扱う意向を有している事業者のパートナー登録制度です。 JALは機内・ラウンジ食のASIA GAP認証食材の採用推進に取り組むことで、食品の安全や、自然環境の保全、生産者の労働安全や人権の保護に配慮し、将来的に持続可能な農産物の供給の実現につなげています。 |
| IFSA (International Flight Services Association)別ウィンドウで開く |  |
機内サービスを提供する航空会社・ケータリング業者などのために設立されたグローバルな専門家による協会で、国際的なガイドライン(“World Food Safety Guidelines”)を定めています。 JALではこのIFSAガイドラインを元にJAL独自の規格基準である「食品安全管理規程」を定め、お客さまに安全・安心な機内・ラウンジのお食事を楽しんでいただくために、提供までのすべてのプロセスにわたる安全管理の仕組みを構築し、日々取り組んでいます。 |
| 自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラム別ウィンドウで開く |  |
自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラムとは、 2023年9月にフレームワークが発表されるTNFDの検討をサポートするステークホルダー組織であり、全世界で1000を超える企業・団体が参画しています。 JALグループは、2023年3月に本フォーラムに加盟しました。 |
| 経団連生物多様性宣言イニシアチブ別ウィンドウで開く | 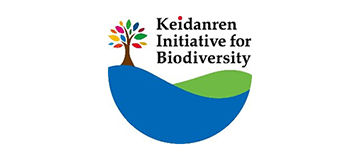 |
経団連および経団連自然保護協議会は、2018年10月に「経団連生物多様性宣言・行動指針」を9年ぶりに改定し、その普及を通じて生物多様性の主流化の一層の促進に取り組んでいます。 こうしたなか、「ポスト愛知目標」の採択をふまえ、日本経済界の多様な取り組み、および「ポスト愛知時代」を見据えた将来の取り組み方針を、企業・団体の顔が見えるかたちで内外に発信する「経団連生物多様性宣言」への賛同を呼びかけ、賛同した企業・団体の「将来に向けた取り組み方針」や「具体的取り組み事例」をとりまとめて「生物多様性宣言イニシアチブ」として公表しました。JALもこのイニシアチブに賛同し、生物多様性の保全に向けて取り組んでいます。 |
| 30by30アライアンス別ウィンドウで開く |  |
30by30(サーティ・バイ・サーティ)とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標です。「生物多様性のための30by30アライアンス」とは、この目標の達成に向け、今後日本として現状の保護地域(陸域約20%、海域約13%)を拡充するとともに、民間等によって保全されてきたエリアをOECMとして認定する取り組みを進めるための有志の企業・自治体・団体によるアライアンスです。JALは2022年4月の発足時に参加し、保護地域、および国際OECMデータベース登録を受けた(受ける見込みの)エリアの管理を支援することを目指しています。 |
| 人的資本経営コンソーシアム別ウィンドウで開く |  |
経済産業省および金融庁をオブザーバーとして設立された「人的資本経営コンソーシアム」に2022年8月より参画しています。このコンソーシアムは、人的資本経営の実践に関する先進事例の共有、企業間協力に向けた議論、効果的な情報開示の検討を行うことを目的としています。 JALは、このコンソーシアムへの参画を通じて、中長期的な企業価値向上を目指し、「人的資本経営」の知見を深め、人財の価値を最大限引き出すための取り組みを積極的に進めていきます。 |
| The Valuable 500別ウィンドウで開く |  |
「The Valuable 500」は、2019年1月に開催された世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)において、「障がい者が社会的活動へ参加できるようになることが、多様な価値を発揮できる社会を創る」という考えのもと、社会起業家のキャロライン・ケーシー氏により立ち上げられた活動です。障がい者が社会、経済にもたらす潜在的な価値を発揮できるような社会づくりを推進することを目的としており、賛同する世界中の企業が加盟し、500社以上の参加を目指しています。JALは2019年より参画し、アクセシビリティの向上に関するコミットメントを発表しています。 プレスリリース(2019年12月26日) |
| 25 by 2025 | 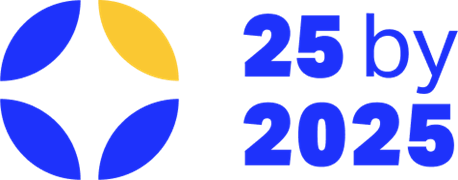 |
世界の航空会社で構成されるIATA(国際航空運送協会)が航空産業でのDEI推進のために2019年から開始した取り組みで、2025年までに管理職(および女性の少ない領域)に占める女性の人数を現行比で25%増加する、または女性の割合そのものを25%以上へと引き上げることを主な目標としています。 JALグループは2021年からこの取り組みに参加し、DEIに関するJALの取り組みを発信するとともに、目標達成に向けて世界各国の航空会社との情報交換を通じ、航空産業のDEI推進に貢献しています。 |
| つなぐ棚田遺産 |  |
農林水産省では、棚田地域の振興に関する取り組みを積極的に評価し、棚田地域の活性化や棚田の有する多面的な機能に対するより一層の理解促進を目的として、改めて優良な棚田を認定する「つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~」を実施しています。JALは2022年よりつなぐ棚田遺産オフィシャルサポーターとして、この取り組みを周知するとともに棚田地域の振興に資する取り組みを促進していきます。 |
| Sedex |  |
Sedexは、エシカル取引サービスを提供している世界有数の会員制組織であり、企業が責任ある、持続可能な事業活動を改善し、「責任ある調達」を行うために必要な実践的なツールやサービス、コミュニティネットワークを提供しています。 JALはSedex会員であり、「責任ある調達」と「倫理的で持続可能なサプライチェーンの構築」に取り組んでいます。 Sedexのツールやサービスの利用を通じて、サプライヤーと共に安全で倫理的、かつ持続可能な事業慣行を維持し、サプライチェーン上で働く人々の労働条件を守ることを目指しています。 |
| パートナーシップ構築宣言別ウィンドウで開く | 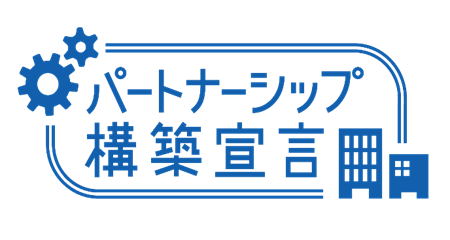 |
「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆さまとの連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを宣言するものです。 JALは、経団連会長、日商会頭、連合会長および関係大臣(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省)をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」が創設した「パートナーシップ構築宣言」に賛同し、当社の「パートナーシップ構築宣言」を2022年9月に公表しました。 |
| 日経ESG経営フォーラム | 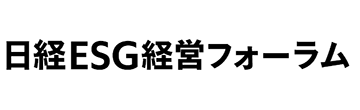 |
日経BPの日経ESG経営フォーラム事務局が「情報発信」「情報収集」「調査・研究」の3つの側面から企業のESG経営をサポートしている会員制組織です。 「情報収集」の分野では、年間30回を超える会員限定のセミナーなどがあります。 JALグループは一般会員として参画しています。 |
| 慶應義塾大学SFC研究所 xSDGラボ xSDGコンソーシアム別ウィンドウで開く |
 |
「xSDGコンソーシアム」は、研究者・企業・自治体が連携して SDGs達成に向けて活動する研究コンソーシアムです。 SDGs研究の第一人者である慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科の蟹江教授が中心となり、 2018年6月に活動を開始しました。 |
こちらの表は横スクロールできます

